ホエールスポーツクラブについて
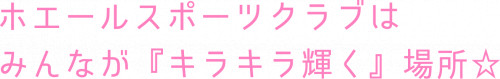
いくつもある体操教室。
「ホエールはどんな所だろう?」「他とどう違うのだろう?」そんな思いで
見て頂いているのではないでしょうか。
大切な時間とお金をかけてする習い事、色々と気になる事が多いのも当然です。
習い事をする理由は様々だと思うのですが、一番大切にしていただきたいのは
「何の為に習い事をするのか?」です。
ホエールスポーツクラブでは
「体操」や「運動あそび」を体験する中で得た、経験や知識を、将来役に立つ
知恵として使いこなせるようになることが大事だと考えています。
また、素敵な人を『自ら考え行動できる人』と定義するならば、必要不可欠な
「考える力」や「チャレンジする力」、周りの人も意識できる「思いやりの気持ち」
また、最も大切な自分を好きになる「自己肯定感」を育むことを大切にしています。
そう!
習い事の目指すべきゴールは、
子どもたちが、将来キラキラ輝いて幸せになること!
ホエールスポーツクラブでは、そのゴールに向かって、いろんな要素をレッスン
に取り入れて、『自分も周りも輝かす』そんな力を育てています。
ぜひ!お子様を輝かすお手伝いをホエールにさせてください!☆